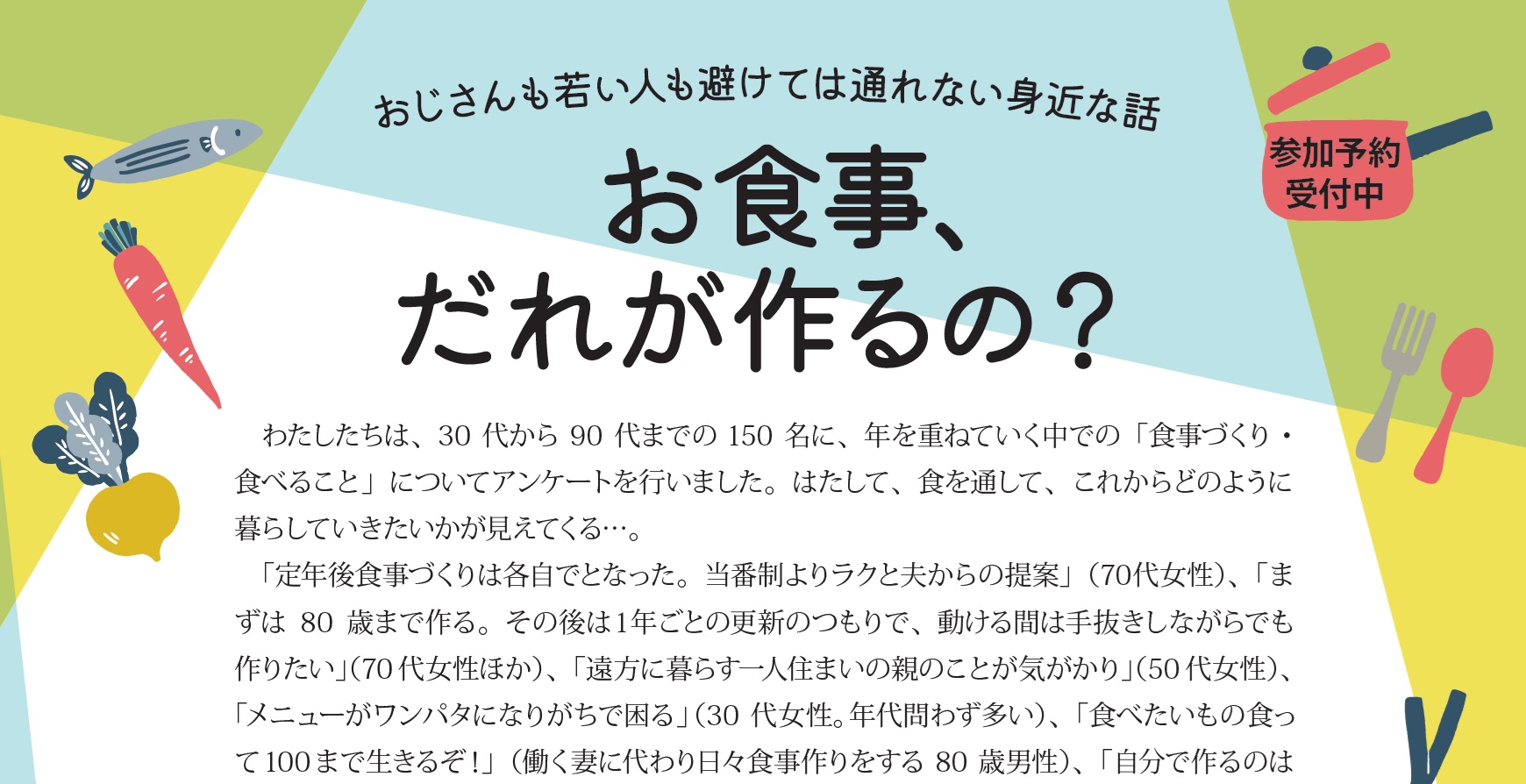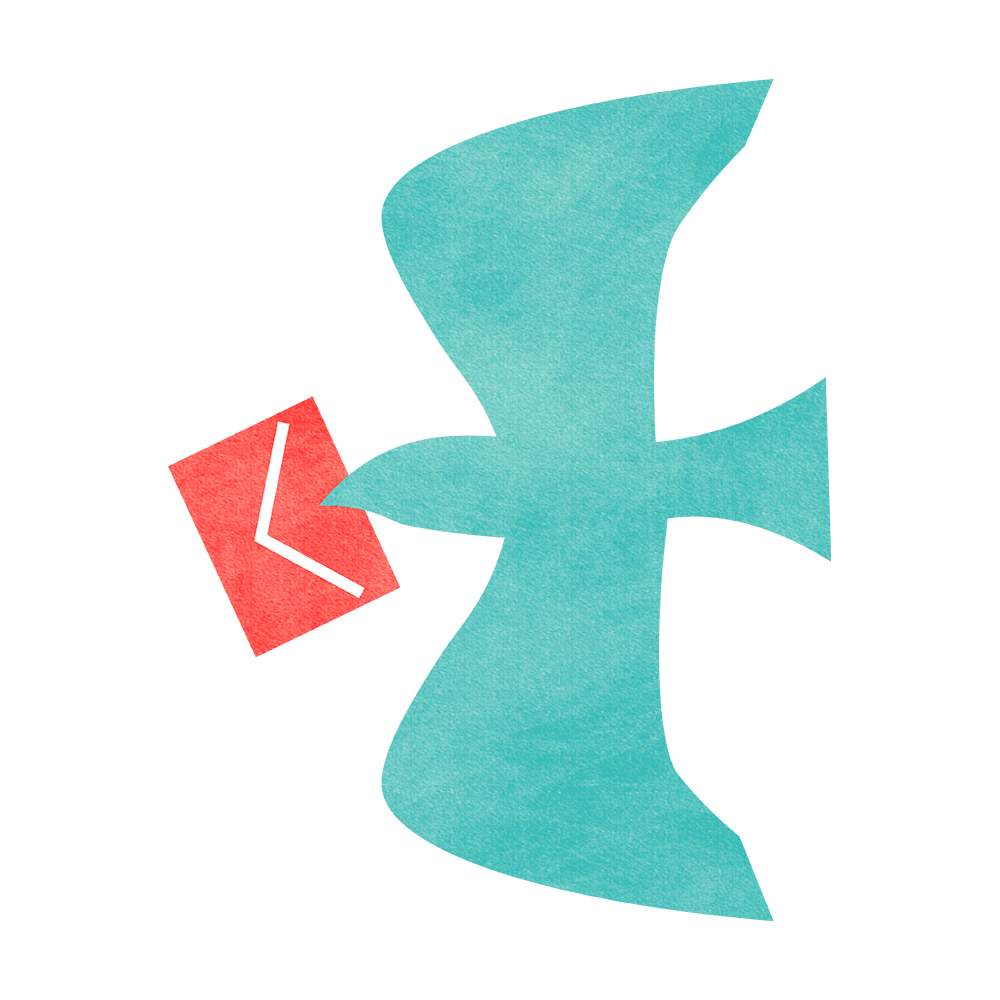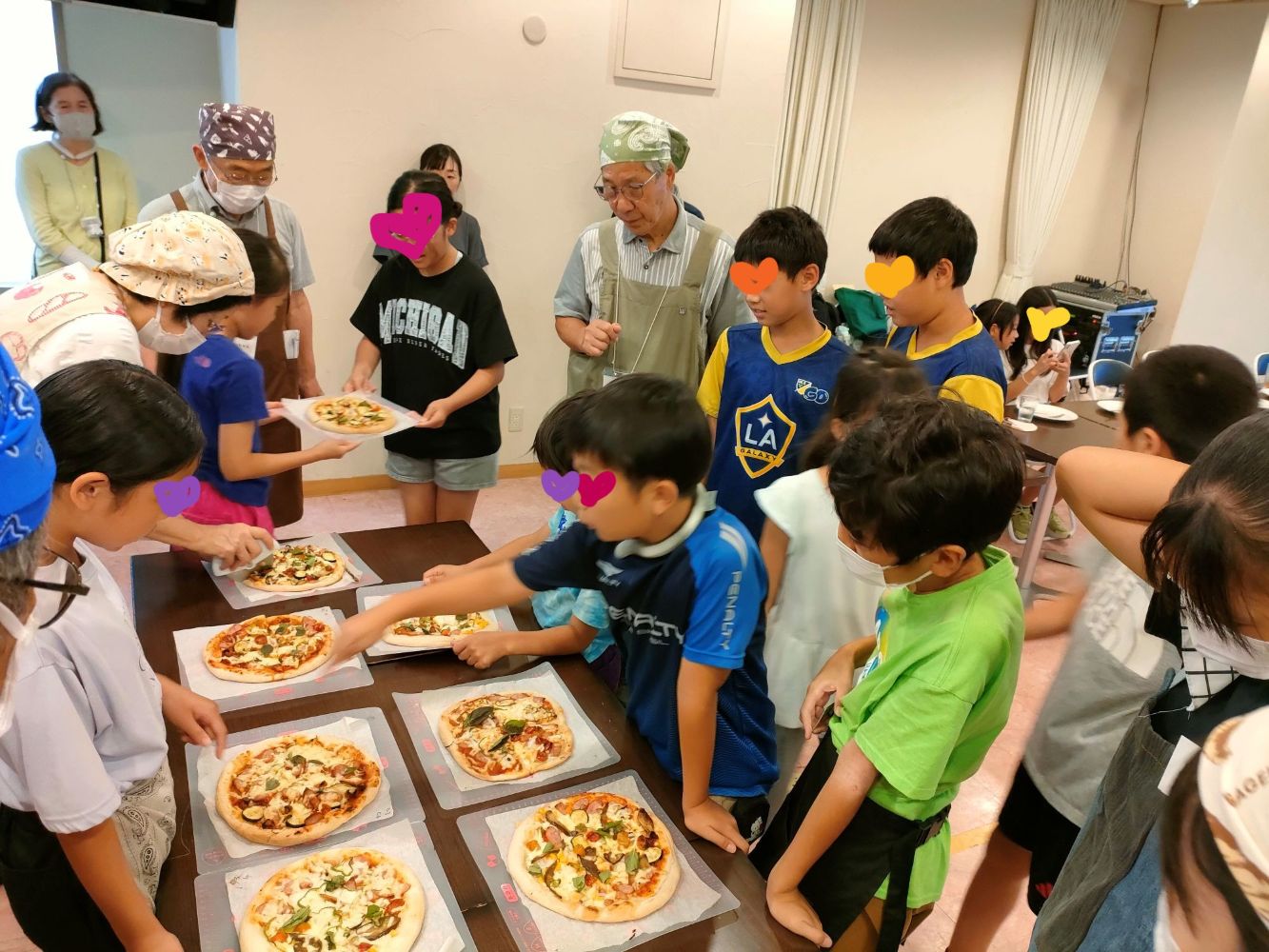パンじいちゃん活動をごいっしょに! シニア男性向け「パンづくり講座」
2026年1月29日・2月12日・2月26日
(さらに…)おひとりさま中華第2弾 ~スーパーのお惣菜大活用編
2025年12月23日(火)
(さらに…)対話型イベント「お食事、だれが作るの?」 ~おじさんも若い人も避けては通れない身近な話
2025年11月29日(土)
(さらに…)子どもと高齢者のためのパン食堂 ~パンづくり体験は2026年3月まで受付中
次回のパン食堂は2月14日(土)毎月第2土曜日に開催
(さらに…)ロクマルのお弁当&地域食堂
お手紙交流会 ~折り紙お手紙
2025年9月17日
(さらに…)小学生とパンじいちゃんのピザづくりレポート
お手紙の書き方プチ講座&交流会
2025年7月23日
(さらに…)